学業活動のなかで、
自分でも気づかない「社会で役立つ力」が育っている。
それが、学業で伸ばせるポータブルスキル=学ポタです。
DSSは、学生の学びに宿る力を見つけて、社会に伝える活動をしています。

学業活動では、知識や専門スキル以外にも、
多くの力が伸びていきます。
たとえば、
レポート提出のために計画を立てる力。
グループワークで意見をまとめる力。
苦手な分野にあえて挑戦する力——。
これらはすべて、
社会でも役立つ“ポータブルスキル”です。
その中でも、学業活動の中で自然と育つ力を、
私たちは「学ポタ(学業で伸ばせるポータブルスキル)」と呼んでいます。
人によって、育つ力も、表れ方も異なります。
たとえば、こんな力が学ポタとして現れます。

出席や課題提出を怠らず、学びを積み重ねる力

履修登録や試験準備を自らマネジメントする力

授業内外で人と協働し、学びを深める力

授業内容を正しく理解し、自分の考えとして整理する力

未知の課題や苦手分野に対して、前向きに取り組む姿勢
これらは一例にすぎません。
学業活動の中には、まだ言語化されていない力がたくさん眠っています。
そして実は、
多くの企業が就職選考で見ているのは、
まさにこのような力です。
面接で聞かれる「どんな行動をしたか」
「困難をどう乗り越えたか」といった問いは、
学生がどんなポータブルスキルを学びの中で身につけてきたかを見極めようとするものです。
つまり、学ポタを意識して育てることは、
社会に出てからの力を高めることと直結します。
今、授業に取り組んでいるその時間が、
未来のあなたをつくっているのです。





自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)といった質問に対し、
学生がAIで整ったエピソードを簡単につくれるようになったことで、
企業側は「本当にその人の力が見えているのか?」という疑問を抱くようになっています。
もともとこうした質問は、学生自身の体験からポータブルスキルを読み取るために使われてきました。
しかし今、それが事実に裏打ちされた評価として機能しにくくなってきているのです。

ただし、これまでの就活では学業は「成績が良いかどうか」「勉強をがんばったか」だけで語られがちで、アルバイトや課外活動に比べて、狭く、矮小化され、ネガティブに捉えられることが多くありました。
しかしそこに、「学ポタ(学業で伸ばせるポータブルスキル)」という視点が加わることで、学業という領域が、「社会で活きる力の宝庫」であることが可視化されるようになってきました。

しかもそれは、履修履歴などの客観的事実とともに確認できる。
つまり、「生成AIによってエピソード評価が難しくなってきた時代」において、企業にとって、学ポタは“信頼できる評価軸”として期待されるようになっているのです。
学ポタは、ちょっとした「意図」で、
ぐんと伸びていきます。
授業に出る、課題を出す、試験勉強をする。
それだけでも立派な学びですが、
「どんな目的で学んでいるのか」
「どんな力を伸ばしたいのか」と
“意図”を持つことで、
あなたの学びは大きく変わっていきます。
学業のすべての場面が、
学ポタを育てるチャンスです。
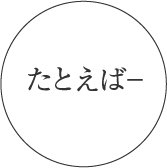
しかも、がんばった事実は履修履歴にも残り、将来、あなたの力を説明する材料にもなります。
DSS(大学教育と就職活動のねじれを直し、大学生の就業力を向上させる会)は、学生の学びが正当に評価される社会を目指すNPOです。
DSSは、学びの中にある“見えにくい力”を、社会に届けていきます。
